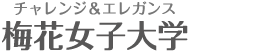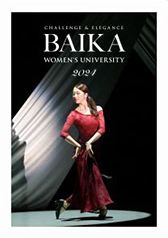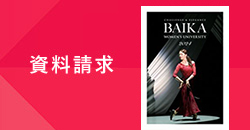中期計画/実施状況報告書 Medium-term plan
梅花女子大学 中期計画(2025~2029)
I.基本目標
梅花女子大学は、1878(明治11)年に創設された梅花女学校を前身としている。従って、この中期計画実施中の2028年に創立150年の節目を迎える。本学園がその創立時より目指した「他者への愛と奉仕の精神を備える自立した女性の育成」という教育目標は、時代とともに形を変えながら脈々と受け継がれてきた。しかし現在の女性を取り巻く環境は、男女雇用機会均等法が施行されて40年近くたっても、一部を除き大きく変わったとは思われない。さらに2024年に世界経済フォーラムが出したジェンダー・ギャップ指数においても、日本は146か国中118位と、特に政治や経済分野での進出が遅れていると言わざるを得ない。150周年のこの節目を迎えるにあたって、本学は創立者澤山保羅先生が志した建学の精神に立ち返り、現代にふさわしい、そして未来を切り開く社会に有為な自立した女性を育成できうる教育体制を再構築していかなければならないと考える。その改革のため、今期の中期計画においては、教育組織のリニューアルとITやAIを利活用した教育システムへの転換が不可避である。
今回策定した2029年度までの中期計画では、業務における自己点検・評価の目標と行動計画を簡潔にまとめた。これらは本学がその質を社会に対して保証するために不断の努力を怠らないことの約束として記したものである。
II.具体的な行動計画
1.大学の使命・目的
1)建学の精神の浸透
「計画」
- (1)学生、教職員に建学の精神を浸透させるために、チャペル・アワー、諸式典、創立記念行事、建学の精神に関する研修会等を見直し、充実を図る。
- (2)建学の精神を明確にし、学内外に向けて的確な情報発信を行う。
2)大学の使命・目的及び教育研究の学内外への周知
- (1)「建学の精神」、「教学の理念」及び「大学の使命・目的」を、内外に向けて情報発信し、周知に務める。
- (2)「建学の精神」及び「教学の理念」の現代的解釈に合致した学部・学科体制へと変革を進める。
- (3)大学・学部・学科の3ポリシーを大学の変革に合わせて再構築するとともに、全教職員への周知を徹底する。
2.学生
1)学生の受け入れ
「計画」
- (1)各学科が求める学生を受け入れるための学者選抜方法については、今後も引き続き検討する。また各学科のアドミッションポリシーや実施方法はホームページ等で広く周知する。
- (2)各学科で定めたアドミッションポリシーに沿った学生が選抜できたかどうかの検証は、各学科が定期的にその選抜方法が妥当かどうかを含め検証する機会を設ける。
- (3)入学定員の安定的充足を目指す。今後ますます重要となるWEB戦略(SNSの効果的な活用等)、オープンキャンパス戦略(コンテンツを含む実施方法等)を考える。
2)学修支援
「計画」
- (1)学生の学修支援として、外部団体等の資格取得に向けて学内にて検定試験を実施する。
- (2)TA(Teaching Assistant), SA(Student Assistant), RA(Research Assistant)の規定を作成し、学習支援の充実に努める。
3)キャリア支援
「計画」
- (1)卒業後を見据えたキャリア意識の醸成、職業選択の可能性を広げるための資格取得の支援など、女子大学としてのキャリア教育およびキャリア支援体制の整備、充実を図る。
- (2)多様化する就職先に合わせた戦略的な就職支援策の確立・充実を図る。
4)学生生活における多様なニーズの把握
「計画」
- (1)学園祭、学長キャンパスミーティング、クラブ交流会等の学生主体の活動を支援し、学生生活の充実を図る。
- (2)学生の多様なニーズに対応する各学科、学生相談室、保健室、ボランティアセンター等との連携による学生生活支援を実施する。
- (3)障害等のある学生の状況把握を行い、合理的配慮を踏まえた修学支援を進める。
5)離学者対策
「計画」
- 学生生活の変容に伴う離学理由の調査、及び改善に向けた対応策を検討する。
6)経済的支援の充実
「計画」
- 学内外奨学金、自治体の修学資金貸付等を活用するとともに、学生の自己管理意識の醸成を図る。
3.教育の質の向上
1)教育内容の充実
「計画」
- (1)ディプロマポリシーに掲げる能力が身についているか検証するための指標を設定する。
- (2)「チャレンジ&エレガンス」を具現できるカリキュラムかどうかの検証を随時行う。
2)教育課程の整備
「計画」
- (1)魅力的なカリキュラムの構築:
「チャレンジ&エレガンス」を具現できる理想の女性の育成を目指して、スリムで魅力的なカリキュラムを構築する。 - (2)カリキュラムポリシー及びディプロマポリシーを組織的に検討し、それらの一貫性の維持に努める。
- (3)学修時間の確保:
各教員は授業準備段階で、学生の授業外学修時間の確保に努める。 - (4)科目ナンバリングの活用と学生指導の徹底:
「BAIKA科目ナンバリングシステム」の改善を年次ごとに行う。 - (5)共通科目としての教養科目および初年次教育に専任教員が関わる仕組みをつくる。
3)教育方法の整備
「計画」
授業実践報告会において、教員が自らの授業における工夫や取り組みを報告し、それを全教員で共有することにより効果的な教授方法の実現を目指す。
4)教育の質保証の確保
「計画」
- (1)GPA(Grade Point Average)制度の厳格化と学生指導等への活用:
GPAを客観的指標として、学生の学修成果の把握及び履修指導等に活用する。 - (2)3つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用:
3つのポリシーを踏まえた学修成果指標を定めた上で、それを公開する。 - (3)学期ごとに授業アンケートを実施し、教育内容・方法および学修指導など、授業改善に努めるとともに、教員からのコメントを公開する。
4.グローバル教育の推進
1)外国語教育および日本文化や異文化理解の充実
「計画」
- (1)オーラル・コミュニケーションに特化した英語クラスの少人数化をはかり、実践的な英語会話力を身につける。
- (2)他の外国語教育の在り方を検討し、充実を図る。
- (3)日本文化および異文化理解に関連する科目の配置を検討する。
2)学外研修の充実
「計画」
学部・学科の学びに沿い、実社会に通用する資格取得や職業体験、国際的な学びを深めることのできる研修プログラムを、国内外の協力機関と連携をはかりながら実施する。
3)グローバル・コミュニケーション・ビレッジ(GCV)の活用促進
「計画」
- (1)全学生を対象に、GCVを英語および他の外国語の実践練習が気軽にできるような場にする。
- (2)留学生や海外研修を終えた学生たちとの交流、さらには英語で触れ合う企画を展開する。
- (3)異文化理解につながる展示および企画を実施する。
5.教育・研究活動
1)教学マネージメントにおける学長のリーダーシップの確立
「計画」
- (1)大学の意思決定機関としての部長会の位置づけを明確にし、議長としての学長からの決定事項伝達の徹底を図る。
- (2)学長は、教学機能効率化のため、職員の適切な配置を検討して実施する。
- (3)学長は、学部・学科が教育課程の編成に必要な人事について適切に採用し、昇任においては分野によらない公正で総合的な教員評価システムを導入する。
2)教育・研究支援センターを中心とする各種FDの取組み
「計画」
授業実践報告や授業参観を通じて、教員相互に授業の研鑽を行う。また、講師を招いての研修会開催や外部研修会への参加を促す。
3)研究支援の確立と実践
「計画」
- (1)研究環境の整備に向けて、各学部に不足している機器等を確認し、充実をはかる。
- (2)全研究者向けに定期的に研究倫理教育講習会を実施し、研究倫理に関するルールを浸透させる。また、学内研究者の実施する人を対象とする研究に関しては、研究倫理審査委員会にて厳正に審査を行う。
- (3)本学の研究者に適した学内外の研究助成の情報をリサーチし、関連する研究者へ伝え、助成金申請や、その採択に向けたサポート体制を充実させる。
6.社会との連携、地域貢献
1)産・官・学連携による、社会貢献のさらなる充実
「計画」
- (1)産官学連携を積極的に授業に取り入れ、実践的授業により産業界に必要な人材育成に寄与する。
- (2)産官学連携を全学生が実施することにより就職活動やキャリア教育として、学生が将来の自立した女性として活躍できる機会とする。
7.経営・管理運営
1)教職員の人事の整備
「計画」
- (1)教員については、学部・学科および大学院の設置基準を遵守し、年齢構成を考えた採用に努める。教育課程は専任の教員で担うことを前提とする
- (2)事務職員についても、将来の担い手の育成を重視し、年齢構成を考慮して採用する。
2)教員の評価制度の構築
「計画」
- (1)昇任審査においては、業績評価項目ごとのポイント制を活用し、総合的に評価することにより、客観性と透明性を確保する。
- (2)通常の教員評価については、学生の授業アンケートを活用し、学長及び学部長による教員評価の点検を実施する。
3)経営の規律と誠実性
「計画」
- (1)法改正に伴う随時の規程・規則類の整備及び遵守を徹底する。
- (2)SDGSの取り組み、ダイバーシティ研修等を実施し理解を深める。
4)SD(Staff Development)の強化
「計画」
- (1)教職員全体のSDについては、「建学の精神」の理解を深める研修会、キャンパスハラスメント研修会、学生の学修状況を検証する研修会等を定期的に開催し、各研修の目的を浸透させる。
- (2)事務職員については、大学および学園の将来を担う者として、果たすべき役割と意識向上を目的とした研修を実施する。
5)財務
「計画」
- (1)学園全体を支える収入の大きな柱は学生生徒納付金と、これに連動する公的補助金収入である。これらの収益源を確保するための努力を不断に続けて行く。
- (2)事業活動収支において経常収支の黒字を確保する。さらには当年度収支において黒字化を目指し、基本金ならびに減価償却引当特定資産の充実を図る。
6)施設設備
「計画」
- (1)経年劣化の状況を鑑み校舎の内外装等リニューアル工事を行う。
- (2)アクティブラーニングやAI活用学習等、デジタル社会に応じた学生の充実した学修を支える環境整備、とくに講義教室のICT化を進めていく。
- (3)本学の学科構成に応じた図書の収集・整備と、利用者が利用しやすい滞在型の図書館運営に取り組むことで、学習の場としての有効的な図書館活動を目指す。また、ガイダンスや利用促進のためのイベント、展示等の実施で図書館運営のさらなる活性化を図る。
8.大学の質保証
1)内部質保証のための組織の整備と
責任体制の確立と自己点検・評価の充実
「計画」
- (1)本中期計画の実施体制は、責任者としての学長の指導のもと部長会が補佐役となり、大学全体で中期計画を実施する。
- (2)学長と部長会は年度ごとの中期計画の実施状況について、恒常的に点検・評価を実施し、各年度における点検・評価と、中間年における点検・評価を計画上に反映する。
2)IR(Institutional Research)を利用した大学運営
「計画」
- (1)学生の現状を把握するための各種調査(GPS-Academic、全国学生調査等)を実施し、分析結果を教職員が把握することにより、教育改革および経営戦略策定等に役立てる。
- (2)授業アンケート、卒業生アンケート(卒業時)を通して、教学を中心とした学生の意見・要望を把握し、教育内容や大学運営の改善・向上に反映させる。
- (3)学内外の各種調査を基にデータの分析を行い、より良い大学教育の実現及び就職支援策の充実を図る。
3)情報公開による説明責任の遂行
「計画」
- (1)梅花女子大学の教育・研究の現状をホームページやSNS、プレスリリース等を通じて広く社会に発信・公表することで、社会に対する説明責任を果たす。
- (2)内部質保証のための、大学の自己点検PDCAサイクルを継続して実施し、その結果を自己点検・評価報告書(梅花女子大学中期計画実施状況報告書)として毎年ホームページで公開する。